普段の料理もお弁当づくりも安全においしく! あらためて確認したい食品衛生のポイント

- ・気温や湿度が高い時期は細菌による食中毒が増える
- ・食中毒対策の基本は「つけない・やっつける・ふやさない」
- ・「大丈夫」と過信するのは禁物!
- ・「低温調理」の加熱は不十分なことが多い
- ・加工食品も使って安全においしく
こんにちは! 食べることが大好きで運動不足がちょっと心配な50代、ビオサポだより案内人のナオさんです。今回も健康な食生活をめざして、さまざまなトピックをみなさんと一緒に探っていきます。
6月の声を聞くと、日本の多くの地域では、そろそろ梅雨入りかなと思えるジメジメした日が増えてきますね。この時期に心配になってくるのが食中毒のリスク。お弁当づくりをしている方は、特に気になっているのではないでしょうか。安心して食事を楽しむために、あらためて家庭でできる食中毒対策について見直してみたいと思います。

気温や湿度が高い時期は細菌による食中毒が増える
少し意外なのですが、実は食中毒は梅雨の時期だけ多いわけではなく、年間を通して発生しています。食中毒の主な原因には、細菌、ウイルス、寄生虫などがあり、その他に自然毒や化学物質なども。気温・湿度が高い時期は特に細菌による食中毒のリスクが高まる、ということなんですね。食中毒対策の基本は「つけない・やっつける・ふやさない」
この春からお弁当づくりを始めた方も多いと思いますが、この時期は特に調理に気を使いますよね。お弁当も含め、食中毒対策の基本は「つけない・やっつける・ふやさない」だと言われます。そのポイントを、お弁当づくりの手順とともに確認していきましょう。
●細菌を食べものに「つけない」
| つけない | |
|---|---|
| 手洗い | 調理の前や調理中に生の肉・魚介類・卵をさわったときなどには必ずせっけんを使って手をきれいに洗う。手や指に傷がある場合は、食中毒の原因となる黄色ブドウ球菌が多くいるため調理用の手袋などで手を覆う。 |
| 清潔なお弁当箱・ 調理器具を使う |
生の肉や魚などに触れた調理器具はよく洗浄し熱湯で消毒する。お弁当箱は、ふたのパッキンも外してブラシ等で細かい部分まで洗い、十分乾かす。 |
| 食材の保存 | 生の肉や魚のドリップなどで他の食べものを汚染しないように、容器を分けるなどして冷蔵庫に保存する。 |
| 食材をよく洗う | 野菜や果実は流水でよく洗う。加熱しないで食べる野菜や果物などに、生の肉や魚の汁がかからないように注意。 |
調理するあいだに手で触れたり、食器・調理器具が触れたりと、食べものに細菌が付着するタイミングは思ったより多いもの。こまめに気をつけるとリスクはだいぶ減りそうです。
●食べものに付着した細菌を「やっつける」
| やっつける | |
|---|---|
| しっかり加熱する | 中心部までしっかり加熱することが大切(中心部が、75℃で1分間以上加熱されていることが目安)。卵焼きやゆで卵などの卵料理は、半熟ではなく、完全に固まるまでしっかり加熱する。火を通さなくても食べられるハムやかまぼこなども、できるだけ加熱調理する。 |
つくってから食べるまでの時間が長いお弁当は特に、しっかり加熱することが大事。朝は忙しくてバタバタしがちなので、時間のゆとりと心の余裕も必要かもしれません…!
●食べものに付着した細菌を「増やさない」
| ふやさない | |
|---|---|
| 水分は大敵 | 水分が多いと細菌が増えやすいため、おかずなどの汁気はよくきる。生野菜や果物はなるべく別の容器に。揚げ物や焼き物など、水分が少ない調理法はお弁当向き。 |
| 冷やしてから詰める | 蒸気が水分となり傷みの原因とならないよう、ご飯やおかずは冷ましてから詰める。 |
| 作り置きのおかずは | 前日に調理するときや昨晩の残り物を利用するときは、詰める前に必ず十分に再加熱する。 |
| 保存も大事 | 冷蔵庫や涼しいところに保管して、早めに食べる。長時間持ち歩くときは、保冷剤や保冷バッグを利用する。 |
私もお弁当をつくるときはいつも、あたふたしながらも『おかずはしっかり冷まさないと…!』と自分に言い聞かせています。暑い時期は、お弁当をよく冷ましてからさらに保冷剤も活躍させています。
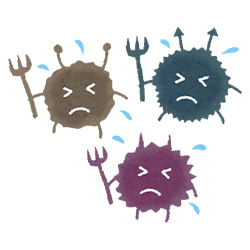
「大丈夫」と過信するのは禁物!
食材は「新鮮だから安全」「新鮮だから生で食べられる」とは限りません。また、日にちの経った食品が安全かどうかは「においや色で判断」ということもよく言われますが、腐敗によるにおいや色の変化がなくても、食中毒菌は増えていることがあるそうです。冷凍しても細菌は死滅するわけではないので、「冷凍すれば大丈夫」というわけでもありません。細菌性食中毒は、十分に加熱することがとても有効な対策。自分で調理するときも外食の際も、しっかり加熱されているかどうかには気をつけたいですね。

「低温調理」の加熱は不十分なことが多い
最近話題の「低温調理」ですが、湯を沸騰させた後に火を止めて、その湯に食材をつけっぱなしにするような調理法は加熱が不十分なことが多いためやめましょう、と食品安全委員会から呼びかけられています。細菌性の食中毒の予防のためには、75℃で1分間の加熱が必要。より低い温度で調理したい場合は、肉の内部温度が70℃になってからさらに3分間、63℃の場合は30分間の加熱を維持する必要があるそう。詳しくは、食品安全委員会(内閣府)が加熱調理について調べた結果をぜひ参考にしてみてください。https://www.fsc.go.jp/foodsafetyinfo_map/shokuhniku_teionchouri.html
加工食品も使って安全においしく
お弁当のおかずにあらかじめ調理された加工食品を利用することは、時短にもなるうえバラエティも豊かになるのでいいですね。生活クラブにも、お弁当向きの加工品がいろいろあります。
 ささみカツ
ささみカツ(カレー風味)
 お弁当用串カツ
お弁当用串カツ
 レンジで!鶏ムネから
レンジで!鶏ムネから
 チキンナゲット
チキンナゲット
 お弁当用チキンレバーハンバーグ
お弁当用チキンレバーハンバーグ
 そのまま
そのまま食べられるおさかなバーグ
 小さな野菜天
小さな野菜天
 3種のおかずセット・豚生姜焼き
3種のおかずセット・豚生姜焼き
 星とハートのスイートポテト
星とハートのスイートポテト
 ピリ辛スティックチキン
ピリ辛スティックチキン
 お弁当用かぼちゃコロッケ
お弁当用かぼちゃコロッケ
 お弁当用かぼちゃグラタン
お弁当用かぼちゃグラタン
わが家でも生活クラブの加工食品は常備してお弁当にフル活用しています! 提携生産者の肉や魚などを使ったおいしさがお弁当でも味わえるのは嬉しいし助かりますよね。みなさんも、これまでに食べてみたことがなかったものなど、ぜひいろいろ試してみてください。
食中毒予防のポイントを押さえながら、安全でおいしい食生活を楽しみましょう!

【参考】
●食中毒は年間を通して発生しています_農林水産省HP
https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/foodpoisoning/statistics.html
●お弁当づくりによる食中毒を予防するために_農水省
https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/foodpoisoning/lunchbox.html
●食中毒予防の原則と6つのポイント_政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/featured/201106_02/#secondSection
●鶏料理を楽しむために~カンピロバクターによる食中毒にご注意を!!~農林水産省
https://www.maff.go.jp/j/fs/campylobacter.html
●「肉を低温で安全においしく調理するコツをお教えします!」_食品安全委員会HP
https://www.fsc.go.jp/foodsafetyinfo_map/shokuhniku_teionchouri.html







